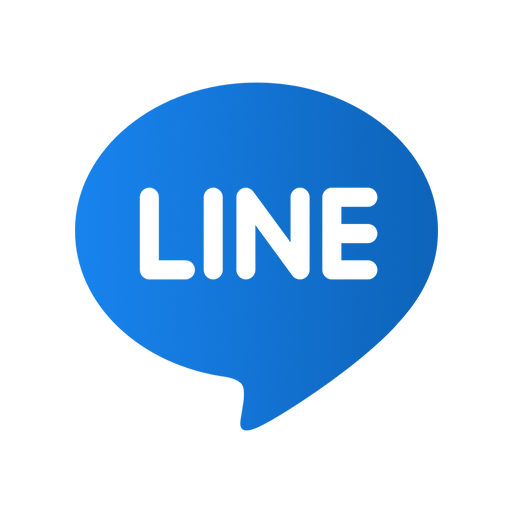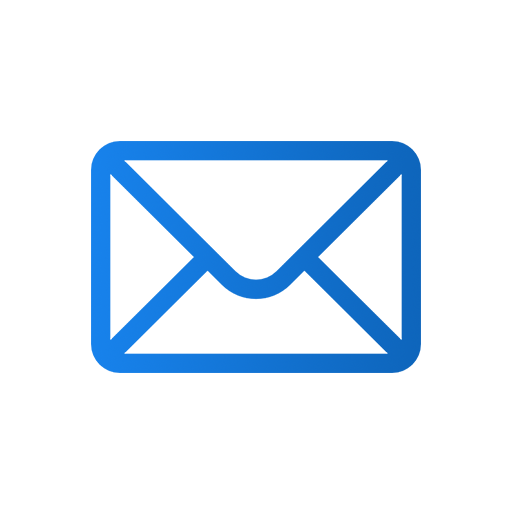米国東海岸港湾労働者が再びストライキを計画、サプライチェーンに新たな打撃の可能性
本日現在、米国東海岸の港湾労働者が1月15日にストライキを再開する計画を発表しました。この動きは、世界的なサプライチェーンに大きな影響を与える可能性があります。国際港湾労働組合(ILA)と米国東海岸港湾事業者を代表する米国海事同盟(USMX)は、賃金交渉で依然として合意に達しておらず、1月7日に交渉を再開し、港湾の自動化に関する問題を中心に議論が行われる予定です。
今回のストライキ計画は、米国東海岸およびメキシコ湾岸の数十の港湾とコンテナヤードを対象としており、太平洋横断運賃の急騰や、既存のサプライチェーンへのさらなる圧力が懸念されています。複数の海運会社は、ストライキが発生した場合、追加料金を課す計画を発表しています。たとえば、マースクは20フィート標準コンテナ(TEU)1個につき1500ドル、40フィートコンテナ1個につき3000ドルの追加料金を設定する予定です。同様に、CMA CGMやハパックロイドなどの他の海運会社も同様の追加料金を導入する方針を明らかにしています。
昨年10月1日にも、米国東海岸とメキシコ湾岸の港湾労働者が労働契約交渉の行き詰まりを理由にストライキを実施しており、数十億ドル規模の貿易が停止し、米国経済および世界のサプライチェーンに広範な影響を及ぼしました。今回の交渉が1月15日までに妥結しない場合、同様の経済混乱が再び引き起こされる可能性があります。
この問題は国際的に注目されており、ストライキが発生した場合、米国の港湾運営が停止するだけでなく、世界の貿易の流れに深刻な影響を及ぼす可能性があります。専門家は、企業が供給網の中断やコスト増加に備えて、早期に対応策を講じる必要があると警告しています。

 米国の港湾労働者のストライキが終了:賃上げ合意に達し、即日復職
米国の港湾労働者のストライキが終了:賃上げ合意に達し、即日復職

 化粧品の新制度が施行され、PFASを含む9種類の成分が禁止されます
化粧品の新制度が施行され、PFASを含む9種類の成分が禁止されます マースク、フランス初の倉庫を開設
マースク、フランス初の倉庫を開設 ヘーパグロイド、40億ドルで24隻のLNG二重燃料コンテナ船を発注
ヘーパグロイド、40億ドルで24隻のLNG二重燃料コンテナ船を発注 LNGの海運燃料としての台頭:排出削減とコスト削減の二重の利点
LNGの海運燃料としての台頭:排出削減とコスト削減の二重の利点