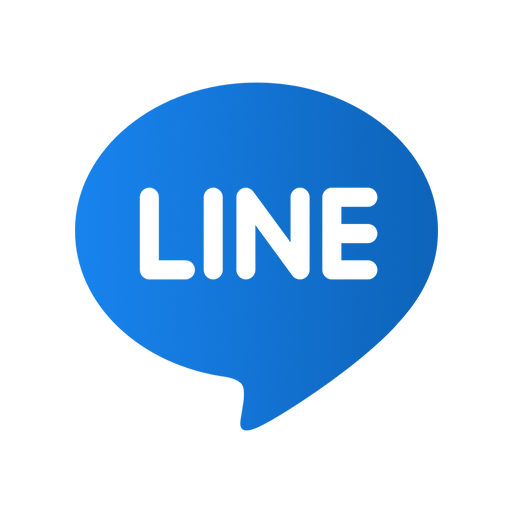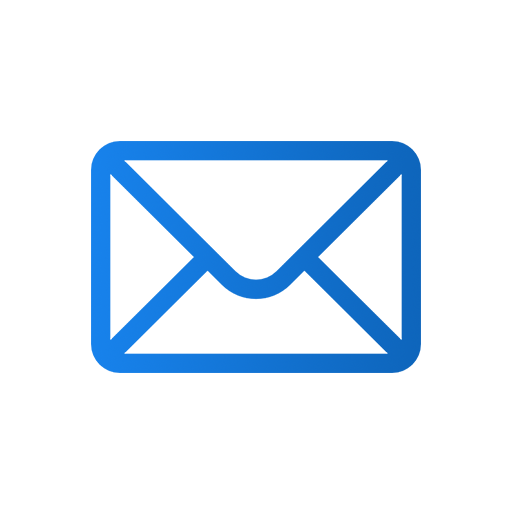三菱ガス化学は2024年度中にも日本国内で船舶用メタノール燃料の供給を開始する。メタノールは従来型船舶用燃料の重油に比べて環境負荷の低い代替燃料として関心が高まっている。4月にはメタノール燃料コンテナ船が横浜港に寄港したほか、年内に内航のメタノール燃料船も就航する予定だ。三菱ガス化学は船舶用メタノール燃料の需要に対応し、供給体制の整備を進める。
ノルウェー船級協会DNVによると、過去12カ月間に新造発注された代替燃料船のうち、メタノール燃料船がLNG(液化天然ガス)燃料船を上回り最も多かった。
メタノールで国内シェアトップの三菱ガス化学は、船舶用メタノール燃料の需要の高まりを見越して、国内で供給するための準備を進めている。船舶向けの供給は初の試みになるため、関係官庁と安全ルールなどに関する検討を行っている。
三菱ガス化学はパートナーと共に、中東など世界4カ所でメタノールプラントを運営。生産能力は年750万トン規模を誇る。日本国内には輸入基地が4カ所ある。それら調達力や既存インフラを生かし、船舶用燃料としての需要に応える。
当初はメタノールの国内輸送に従事しているメタノール輸送船を燃料供給船として転用することを想定。需要に応じて、メタノールバンカリング(燃料供給)船を新造することも視野に入れる。
船舶用メタノール燃料は、天然ガスから生産されたグレーメタノールだけでなく、海運会社の需要に応じてバイオメタノールやグリーンメタノールなど非化石燃料由来のメタノールも供給する。
バイオや特に初期のグリーンメタノールは供給量が限られる。価格も高くなることが予想される。そのため、「グレーメタノールにブレンドして供給することが多くなるのではないか」(三菱ガス化学関係者)。
メタノールは従来型の船舶用燃料に比べて環境負荷が低いことが特長だ。
SOx(硫黄酸化物)の排出量は従来型の燃料に比べ最大99%、PM(粒子状物質)は最大95%、NOx(窒素酸化物)は最大80%、グレーメタノールでもCO2(二酸化炭素)の排出を最大15%削減できる。
メタノールは常温常圧で液体のためLNGやアンモニアなどに比べて取り扱いが容易、エンジンなどの技術も確立されている、燃料供給インフラも既存設備を活用できる―といった利点もある。
バイオガス由来のバイオメタノールや工場などから回収したCO2と再生可能エネルギー由来の水素で製造されるグリーンメタノールを活用すれば、GHG(温室効果ガス)排出量のさらなる削減も見込まれる。
一方、「カーボンクレジットの扱いなどが課題になる」(同)。海外で排出されたCO2を利用して製造されたメタノールを国内で使用した場合、カーボンニュートラルと見なされるのかどうかなど、認証体制の整備はこれからになる。
DNVの統計では、世界で就航済みのメタノール燃料船は35隻。発注残は269隻まで増加した。船種はタンカーやコンテナ船のほか、バルカー、自動車船、クルーズ船などに多様化している。
メタノールの世界の需要は年9200万トン規模。発注済みのメタノール燃料船が就航すれば、800万―1000万トンの燃料需要が創出されるとの試算もある。
船舶用メタノール燃料は、当初はメタノールを貨物として輸送するケミカルタンカーでの利用が主だった。ケミカルタンカー以外では、コンテナ船大手のマースクが初めて採用。他船社での採用も急激に増加した。
マースクは4月には、1万6000TEU型のメタノール2元燃料船を横浜港に寄港させた。同社は横浜市、三菱ガス化学とメタノールバンカリングに関する覚書も結んでいる。
環境対応を積極的に進める日系海運会社でも、メタノール燃料を採用する動きが活発化している。
今年1月には海運大手3社が出資するオーシャンネットワークエクスプレス(ONE)がメタノール2元燃料1万3000TEU型12隻の発注に踏み切った。
商船三井ドライバルクは神原汽船からメタノール2元燃料中型バルカーを定期用船することを決めた。NSユナイテッド海運も主に鉄鋼原料を運ぶ大型バルカーでメタノール燃料を採用する。
三菱ガス化学は用船者の立場では、同社が輸入するメタノールを運ぶタンカーにメタノール2元燃料エンジンを搭載する。商船三井から長期用船し、25年から運航を開始する予定だ。三菱ガス化学は運航船をメタノール燃料船に順次切り替えていく方針だ。
引用至《日本海事報》2024年06月17日 デイリー版1面
![]()
![]()
![]()



 契約締結した(左から)武市社長、奥村社長、三菱造船・上田伸社長
契約締結した(左から)武市社長、奥村社長、三菱造船・上田伸社長 C1ケミカル事業部の松川将治氏(右)と三嶋悠之氏
C1ケミカル事業部の松川将治氏(右)と三嶋悠之氏 混雑はマレーシアにも広がる(写真はポートクラン)
混雑はマレーシアにも広がる(写真はポートクラン) 発注残は既存船の4割に相当する
発注残は既存船の4割に相当する