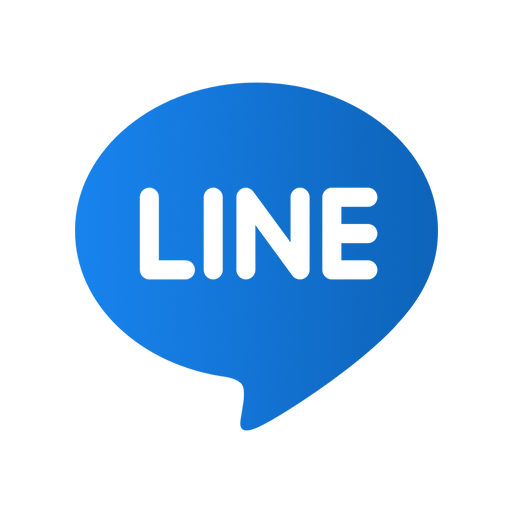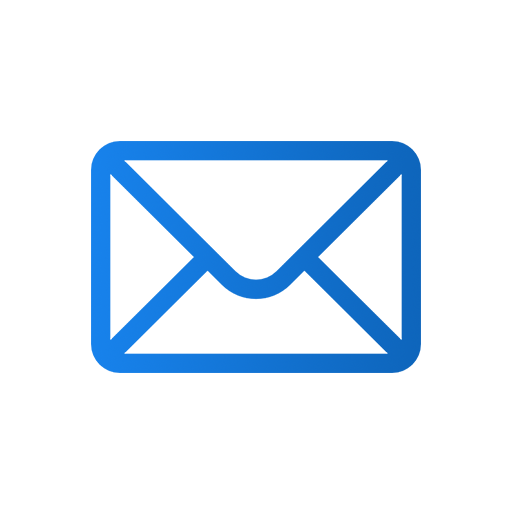世界初の電気運搬船の実現などに取り組むスタートアップ企業、パワーエックス(伊藤正裕社長)は23日、電気運搬船を開発・販売する新会社「海上パワーグリッド」を設立したと発表した。初号船「X」(100TEU型)の2026年後半の商業運航開始に向け、同社を通じ海上送電事業を加速させる。同時に電気運搬船よりコストを抑えられ、平水海域に適した電気運搬バージのデザインを新たに公表。船とバージを戦略的に併用し、運用効率と経済性の向上を図る。船舶用蓄電池の量産体制構築もこのほど完了し、電気運搬船の実現をいよいよ射程に捉えた。
海上パワーグリッドは2月9日、パワーエックスが展開してきた船舶・風力発電事業とその専門技術の移管を受け、同社の100%子会社として発足。電気運搬船の開発・保有・販売や同船を用いた海上電力輸送、電力販売、船舶用蓄電池の販売などを手掛ける。代表取締役は伊藤氏が兼務する。
新会社は今後、海運・造船や電力・エネルギー企業などを対象とした第三者割当増資を2段階で実施。初号船の建造費用や設計開発費用、新会社の運転資金を含め「100億円以上の資金を調達する計画」(伊藤社長)だ。
海上パワーグリッドは現在、100TEU型の電気運搬船「Power Ark 100」の初号船「X」の完成に向け、詳細仕様書を作成中。今夏をめどに詳細設計を終え、型式承認や試験運航などを経て、25年前半に受注・建造を開始し、26年後半の竣工・商業運航を目指す。
同船は全長147メートル、幅18・6メートル、喫水6メートルの電気推進船で、船倉にパワーエックス製の20フィートコンテナ型の船舶用蓄電池96本を搭載する。バッテリー容量は240メガワット時と、一般的なEV(電動)内航船が3・5メガワット時であるのに対し超大容量。21年末にパワーエックスへの出資をいち早く決め、電気運搬船の共同開発に乗り出した今治造船が建造する。
海上パワーグリッドはこの「Power Ark」の派生モデルとして23日、短距離で穏やかな平水海域での運用に最適なバージ型電気運搬船「Power Barge」のコンセプトを明らかにした。
「Power Barge」は全長約81メートル、幅30メートル、載貨重量約6000トンの大型バージ。「Power Ark」と同じく20フィートコンテナ型の船舶用蓄電池96本を搭載し、一度に最大240メガワット時の電力を輸送できる。
船体はいかだ形状で瀬戸内海などの波高が低い海域での使用に最適化。「Power Ark」と比べてコスト低減が可能なモデルとして設計された。
同バージは船体の仕様から電気運搬船より建造費用が安く済む。また推進機関を持たずタグボートが曳航するため、配乗が必要な船員はタグボートに5人程度で済み、船員15人で運航する「Power Ark」に比べて運航コストを抑制できる。
海上パワーグリッドは、電気運搬船を水深2000メートルまでの遠距離で波の荒いエリア、電気運搬バージを有義波高1メートル以下の近距離で波の穏やかなエリアと、需要家の用途に応じて併用していく。
「Power Barge」についても「需要家との協議次第だが、26年後半には商業運航を始めたい」(同)考えだ。同船の建造ヤードは「今治造船と協議を進めている」(同)。
またパワーエックスは岡山県玉野市に建設した日本最大級の蓄電池工場「Power Base」でこのほど、船舶用蓄電池の量産体制の構築を終えた。具体的には、コバルト不使用で発火しないLFP電池(リン酸鉄リチウムイオン電池)を使用した船舶用蓄電池モジュールの自動化生産ラインを完成した。
同モジュールは150個を20フィートコンテナ型の船舶用蓄電池に仕立てるため、96本搭載する電気運搬船・バージ1隻当たり1万4400個が必要。これを「年間15―16隻分生産できる体制が整い、25年7月から量産を開始する計画」(同)だ。
伊藤社長は日本海事新聞の取材に対し「船級協会の認証を前提とした生産ラインが完成し、世界でも前例がない舶用LFP蓄電池の量産体制が整ったことは大きな節目だ」と強調。荷主との商談も複数進んでいるといい、「いよいよ電気運搬船を建造・実現するフェーズに入る」と語った。
■【解説】洋上風力新市場に照準。海上電力インフラ会社へ
日本近海の洋上風力発電所でつくられた電気を、大型蓄電池を搭載する電気運搬船で陸上に輸送する―。このビジョンを掲げて創業したパワーエックスの電気運搬船事業に強力な追い風が吹いている。
政府が先月12日、洋上風力発電の設置場所を現行の領海内から排他的経済水域(EEZ)に拡大する「再生可能エネルギー海域利用法」の改正案を閣議決定したからだ。
洋上風車を設置可能なエリアが領海内に限られていた日本の洋上風力はこれまで、浮体式で水深300メートルまでの海域への設置を前提に発電量を算出。この結果、国内の洋上風力のポテンシャルは現状、着床式と浮体式を合わせて約550ギガ(ギガは10億)ワットとされている。
法改正に伴い、洋上風車の設置可能な場所がEEZまで拡大。パワーエックスはこれにより、水深300―2000メートルの海域で約2000ギガワットの洋上風力の新市場が生まれると試算する。
しかも、その市場にアクセスできるのは現状、電気運搬船だけだ。
洋上風力と本土を接続する海底ケーブルの敷設は、水深300メートルまでは日本でも一部実績がある。しかし、300メートルより深い海域でのケーブル敷設は現行技術では不可能とされ、実績がない。
洋上風車の設置範囲が水深2000メートルの海域まで広がると、電力需要が特に大きい関東沖と北海道沖、中部沖の風況・風力が特に強い。パワーエックスはここから電気を電気運搬船で陸上に輸送することで、「関東を洋上風力の一大拠点とすることが可能だ」(伊藤正裕社長)とみている。
実際に洋上風力の新市場が立ち上がり、電気運搬船で輸送可能となった場合、陸側の受け入れ体制はどうなるのか。
パワーエックスが想定するのが、廃炉となった火力発電所の活用だ。2030年までに廃炉を決定済みの火力発電所は全国に17カ所あり、廃炉予定を含めるとその数はさらに増える。
廃止された火力発電所はいずれも港湾に隣接しており、石炭船バースなど電気運搬船が寄港できる岸壁が既にある。その上、電気を送る系統線が最大の需要地である市街地に直結されており、ほぼ使われていない。
このため、例えば関東沖に立ち上がる洋上風力から、三浦半島(神奈川県)の火力発電所に電気運搬船で電気を輸送すれば、「東京と首都圏に膨大な電力を低コストで流し込める」(同)。
政府が莫大(ばくだい)な予算を投じて計画している、国内電力各社の管轄エリアをまたぐ「系統間送電」向けケーブル新設の大部分が不要になるというわけだ。
日本では環境対策として、火力発電所を段階的に廃止する計画が進行中。その一方、30年までに太陽光や風力などの再生可能エネルギーが全電源の30%以上を占めると予測されている。
加えて原子力発電所の再稼働が進む中、再エネ由来の電力の過剰供給による出力制限の回数は今後、九州や中国地方を中心にさらに増加する見通しだ。
これらの課題を解決するには、電力需要地と再エネが豊富な地域間の系統接続の強化が不可欠。だが、地域間連系線の整備には莫大な費用と時間が必要になる。
海上パワーグリッドはこうした状況に対し、電気運搬船を水深2000メートルまでの遠距離で波の荒いエリア向け、電気運搬バージを有義波高1メートル以下の近距離で波の穏やかなエリア向けに併用。系統を機動的に補完する新しい送電手段を提供し、「日本の電力インフラの改善に寄与する公共性が高い海上送電会社」(同)を目指す。
引用至《日本海事報》2024年04月24日 デイリー版1面

 (左から)光田氏、クリストファーソン氏、ライリー氏、ハバード氏
(左から)光田氏、クリストファーソン氏、ライリー氏、ハバード氏 造船業を下支えする協力会社の技能工(写真提供=日造協)
造船業を下支えする協力会社の技能工(写真提供=日造協) グリマルディは船舶投資も積極化(KNUD E.HANSENのホームページから)
グリマルディは船舶投資も積極化(KNUD E.HANSENのホームページから)