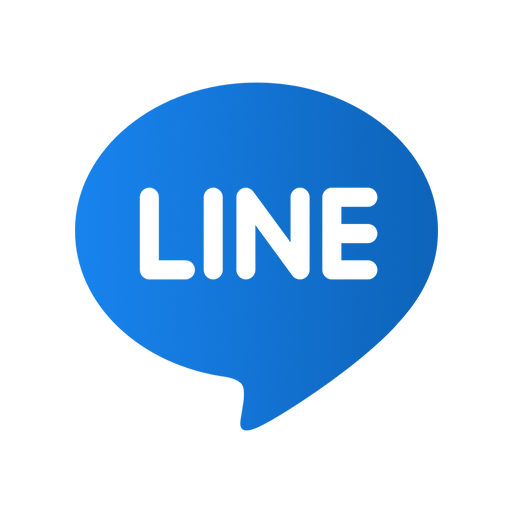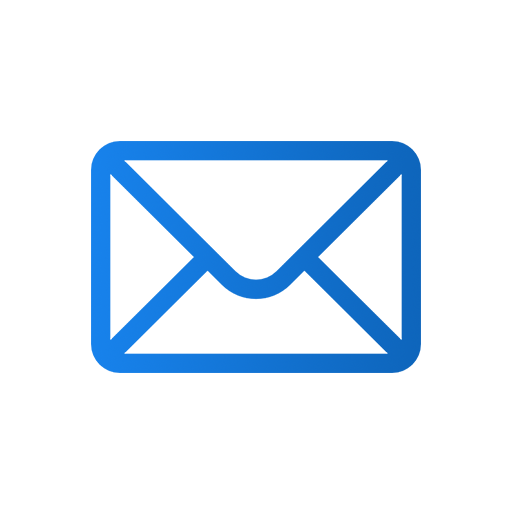日本食品の国境検査措置 (最新の情報9/26)
一、輸入停止查驗品目及其生產地區
- 停止輸入查驗品目及其生產地區:
- 日本厚生労働省発表の「出荷制限一覧表」に記載されている流通制限品目およびその生産地の製品は、輸入検査停止対象とします。
- 日本から食品を輸入する報告義務者は、「輸入食品及び関連製品申請書」の製造工場コード欄に、付表に記載された都道府県名を繁体字中国語で記入してください。
- 第一点に規定された製品の適用は、輸出日を基準とします。
二、日本からの食品輸入には産地証明書が必要
日本から食品を輸入する際には、以下のいずれかの産地証明書を添付し、輸入食品検査を申請する必要があります:
- 日本の公式機関が発行する産地証明書。
- 日本の公式機関またはその認可機関が発行する産地を証明する書類、または当署が認可した産地証明書。
- 上記書類には、都道府県名までの産地情報が記載されていることが必要です。
三、日本の特定食品輸入には放射線検査証明書が必要
- 放射線検査証明書を添付すべき特定食品の品目:
- 福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県で製造された製品。
- 前点に規定された製品の適用は、輸出日を基準とします。
四、日本食品の規制措置に対応するための輸入食品声明の提出
- 衛生福利部の2022年2月21日付公告(衛授食字第1111300354号)および2024年9月25日付公告(衛授食字第1131302719号)に基づき、「食品及び関連製品輸入検査方法」第4条第2項に従って行います。
- 前述の公告は、日本国内で流通が制限されている品目およびその生産地の製品の輸入検査停止を規定しています。
- 自主管理責任の実施のため、2022年2月21日以降(輸出日基準)、
- 日本食品を輸入申告する際、毎回「輸入した食品が日本国内の流通制限品目に該当しない」旨の声明または証明書を提出する必要があります。
- 日本食品(成分に野生動物肉、キノコ類、菜の花油を含む)を輸入申告する際、毎回「輸入した食品に日本の5県の検査停止品目が含まれていない」旨の声明または証明書を提出する必要があります(2024年9月25日以降の輸出日には適用されません)。
- 前述の声明は、「添付書類の種類」欄に「99-その他」を選択し、「添付書類番号」欄に声明文または証明書を記入してください。
- もし報告義務者が虚偽の情報を提供したり隠蔽したりして公務員が虚偽の記載を行った場合、刑法第214条の「公務員による虚偽記載罪」または第215条の「業務上虚偽記載罪」に問われる可能性があります。
文章轉載至為【衛生福利部食品藥物管理屬】

 日本食品の国境検査措置 (最新の情報9/26)
日本食品の国境検査措置 (最新の情報9/26) 米国の港湾労働者のストライキが終了:賃上げ合意に達し、即日復職
米国の港湾労働者のストライキが終了:賃上げ合意に達し、即日復職
 米国郵政:本日より中国・香港からの荷物の受け入れを停止
米国郵政:本日より中国・香港からの荷物の受け入れを停止